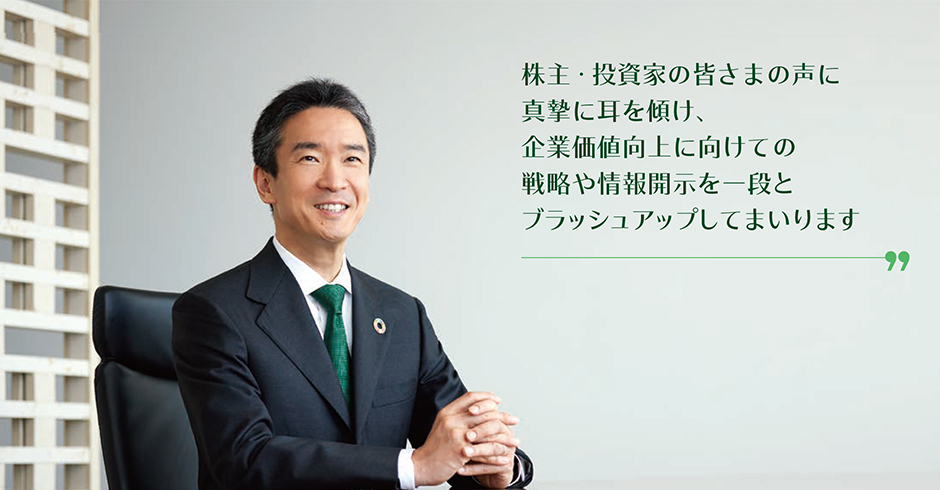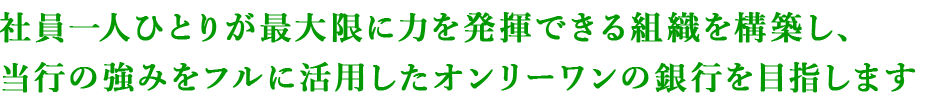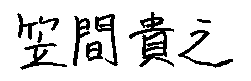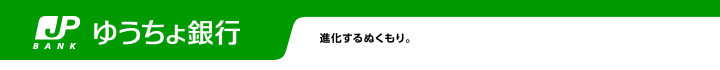
ホーム > IR情報 > 決算・IRライブラリ > 統合報告書・ディスクロージャー誌 > トップメッセージ
トップメッセージ
金融機関としての重責を改めて感じた1年
2024年4月の社長就任以来、1年が経過しました。この1年を振り返ると、まずは就任直後のシステムの不具合を思い出します。他の金融機関から当行への入金が遅延する事象が発生し、また、2025年4月にもゆうちょダイレクト、ゆうちょ通帳アプリなどにおける一部のサービスが一時的に提供できない事象が発生しました。
混乱が広がることのないよう迅速な情報収集と舵取りに努めましたが、システムトラブルが発生した際に、安心・安全な金融サービスを提供するという当行の金融インフラとしての使命の大きさを再認識しました。当行は、日本の全人口にも匹敵する約1億2千万もの貯金口座を有しており、さまざまな決済チャネルを通じて、日夜問わずお客さまにご利用いただいています。当行のシステムは、日本でも最大規模の銀行システムであり、世界でも屈指の取引量を処理していると考えています。これだけ膨大な取引を維持・運用する盤石なシステムを構築した先人たちのご尽力には頭が下がる思いですし、同時に、日本全国のお客さまにご利用いただいていることの責任の重さを痛感しました。
当行を取り巻く経営環境に目を向けると、2024年には日本銀行によるマイナス金利政策の終焉により、いわゆる「金利のある世界」が本格的に到来し、市場環境は大きく変化しました。足許では米国の通商政策をはじめ、国際情勢も、地政学リスクも含めて刻々と変化しています。米国の政策はドル金利や為替にも影響し、それが翻って、私たちにとって最も重要な指標のひとつである円金利にも波及しますので、特に注視しています。
また、2025年3月には、日本郵政による当行普通株式の第三次売出しが実施され、日本郵政の当行に対する議決権比率は50%を下回りました。今後、新規業務展開の機動性や自由度がいっそう高まることとなり、これは当行の中長期的な成長を加速するうえでも大きな進展です。社長就任1年目でこれらの変化を目の当たりにし、経営を取り巻く景色がガラッと変わった、そのような印象です。社長とは、会社という大きな船の上で常に役職員の先頭に立ち、よき未来へと導いていく船頭のようなものであると思っていますが、環境が変わり、改めてその役割が重要であることを実感しています。
機動的なポートフォリオ運用で3期連続の上場来最高益を目指す
2024年度の連結当期純利益は、4,143億円となり、2期連続での上場来最高益を更新しました。また、株主の皆さまへの配当も、前年度から7円増配の1株あたり58円と、順調に拡大しました。
2025年度の連結当期純利益見通しは4,700億円とし、配当については、利益成長の拡大に応じて2024年度から8円増配の1株当たり66円とする計画です。
好調な業績の要因を分析すると、やはり、勝負どころを逃さずにスピード感をもって動いたことが大きいと感じます。具体的には、円金利の上昇トレンドを捉えて、円金利ポートフォリオの再構築方針を決定し、日本国債への積極的な投資を進めてきました。仮に当行の投資対象である中長期の日本国債、例えば10年の日本国債を毎年10兆円程度購入していくと仮定すると、2024年度投資分の10兆円、2025年度投資分の10兆円と毎年の投資による収益が重層的に積み上がり、将来にわたって収益効果が安定的に続くことになります。現在償還している日本国債は利回り0%程度ですので、新規投資していく10年の日本国債が利回り1.5%程度とすると、収益の増加要因となります。
もちろん、マーケットは常に変動しますから、10年の日本国債を買い入れるにしても、イールドカーブ(利回り曲線)全体を見て、他の年限の日本国債対比で割高になってきたら購入年限を見直すといった都度の調整を図るなど、機動的かつきめ細かに投資を進めてきました。マーケット動向や当行のポートフォリオのチェックは、社長に就任した今も私の基本作業です。少しでも気になるところが出てくれば市場部門やALM企画部と話し合っており、投資のリスクとリターン、調達コストと投資利回り、資産・負債のバランス、取得しているリスク量の状況などについて、常に細かくモニタリングしています。
円金利の上昇は収益増加要因である一方、これにより、日本国債を中心とした「その他有価証券」の評価損が拡大しています。ただしこれは、想定の範囲内のことであり、当行はさまざまな手法によって評価損拡大の抑制等に取り組んでいるため、財務の健全性維持に問題はありません。
市場との対話で経営の方向性を確認
社長就任以降、さまざまなステークホルダーの方々との対話の機会を数多く持つことを心掛けてきました。海外投資家を含む資本市場の皆さまからは、当行の株価ひいては成長ストーリーへのご期待の声を数多くいただきました。「金利のある世界」において、私の考える経営の方向性が投資家の方々の描くストーリーと大きく乖離していないことを確認できたとともに、改めて投資家の皆さまからのご期待にしっかりと応えていかなければならないとの思いが強くなりました。
特に、資本市場の皆さまとの対話で改めて感じたこととしては、「金利のある世界」となって、当行独自の強みである「約1億2千万口座のお客さま基盤」、「約190兆円のリテール中心の貯金残高という安定した資金基盤」が評価されており、この当行独自の強みを維持・発展させていくことが当行の企業価値向上のため重要であるということです。
終わりなき風土改革が「変革」を加速する
社員との対話に関しては、社員の声とお客さまの声を直接経営に活かす取り組みとして、社長直轄の組織横断的な専門委員会である「みんなの声委員会 -ECHO-」を設置しました。私はその委員長として、若手社員と膝を突き合わせた本音の議論、タウンホールミーティング(社員との対話集会)や社員との1on1ミーティング、WEB社内報等を通じた社内コミュニケーションなどを通じた対話の機会を大切にしてきました。
また、全国の拠点をこの目で直接見たいと考え、全国行脚にも精力的に取り組んでいます。昨年の統合報告書でも紹介しましたが、当行の強みは、国営の時代から「お客さまに寄り添い、社会・地域への貢献を果たそうとする、一人ひとりの社員の真摯な姿勢」によって長年醸成された企業風土であり、それが当行に対するお客さまからの信頼の土台であると考えています。全国の拠点訪問を通じて、私はこの当行の財産というべきカルチャーを改めて実感しています。
そのうえで、「みんなの声委員会 -ECHO-」を中心に、商品・サービスの改善や向上、社内コミュニケーションの円滑化、さらには組織力向上を通じた価値創造に向けて、組織横断的に取り組んでいます。この委員会活動に共感する社員がさらに増え、その思いが波紋のように広がり、全国の拠点へと伝播していく、改革マインドにあふれる組織を目指していきたいと考えています。「みんなの声委員会 -ECHO-」の活動については、参加している社員の熱量や創意工夫が想像以上で、ポジティブサプライズが多いです。風土改革はゴールのない取り組みながらも、想定以上に進捗していると感じており、今後さらによくなる手ごたえがあります。
中期経営計画のビジネス戦略
冒頭申し上げたように、当行を取り巻く外部環境は大きく変化しています。国内外の金利変動のほか、キャッシュレス・生成AIなどのデジタル化の急速な進展、そして人口減少・超高齢社会などに代表される社会構造の変化に対しても、10年先、20年先を視野に入れて対応を進めていかなければなりません。
そのような中で、2024年5月に中期経営計画を見直し、「リテールビジネス」、「マーケットビジネス」、「Σ(シグマ)ビジネス」という3つのビジネスを成長の核とする戦略を打ち出しました。いずれも、「約1億2千万口座のお客さま基盤」、「190兆円を超える資金基盤」、「全国に広がる2万を超える郵便局ネットワーク」という当行独自の強みを最大限に活かし、当行ならではのオンリーワンのビジネスを推進する戦略です。
リテールビジネス
~オンリーワンのリテールビジネスモデルを構築~
リテールビジネスについては、「リアルとデジタルの相互補完」、「共創プラットフォーム」、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」をキーワードに、新しいビジネスモデル構築を進めています。
「リアルとデジタルの相互補完」とは、デジタル化の波に対して「リアルかデジタルか」の二者択一で対応するのではなく、「リアルでもデジタルでも」と両面で進めていく戦略です。デジタル対応の要となるバンキングアプリ「ゆうちょ通帳アプリ」の登録口座数は、2025年3月末現在で1,359万口座と、目標としていた1,300万口座を突破し、さらに拡大中です。2026年3月末には1,600万口座、2029年3月末には2,500万口座突破を目標としており、日本の人口の4~5人に1人が利用するアプリを目指しています。
店舗(リアル)ネットワークでは、全国に毛細血管のように張り巡らせている窓口での親切・丁寧なご案内を基本としつつ、ATMの高機能化、お客さまが手続きをセルフ処理できる窓口タブレットの直営店への配備、お客さまの資産運用コンサルティングを専門とする社員を配置したリモート拠点とのオンライン相談等を通じて、お客さまのニーズに合わせたサービスチャネルの強化に努めています。なお、店舗ネットワークは、デジタル時代にこそ、その強みを発揮できると考えます。すなわち、「ゆうちょ通帳アプリ」のご利用を店舗でしっかりサポートすることで、デジタルに不慣れなお客さまにも便利なデジタルサービスをご利用いただけるように努めています。
「共創プラットフォーム」とは、パートナー企業と連携して当行単独では提供できなかった多様で新しい金融商品・サービスを開発してラインアップの充実を進め、それらを、当行が保有するお客さまからの利便性が高いリアルとデジタル2つのサービス提供チャネルのうち、最適なチャネルを通じてお客さまにお届けするという構想です。
「DX」については、「ゆうちょ通帳アプリ」の機能向上、ATMの高機能化、窓口タブレットの配備等のほか、業務フロー効率化の観点からも強力に推進しています。当行では、全国各地の郵便局を営業・事務両面からサポートするパートナーセンターに加え、貯金事務センター、コールセンター等の社員が業務を堅確に遂行していることが、お客さまの当行への信頼の礎となっています。これをいっそう強化すべく、貯金事務センターへのAI、RPA(ソフトウェアロボットによって定型業務等を自動化する技術)、BPMS(業務フロー全体のデジタル管理システム)等の導入、コールセンターへのAIを活用したチャットボットの導入等、戦略的・積極的なIT投資を通じて、抜本的な業務フロー改革を進めています。
「リアルとデジタルの相互補完」、「共創プラットフォーム」、「DX」の掛け算により、抜本的な業務フロー効率化を進めつつ、日本全国あまねく誰にでも、世代を問わず、あるいは日本に住む外国籍の方々も含め、「誰一人取り残さない」という精神で、安心・安全・便利な金融商品・サービスを伝統的な銀行業務の枠を超えて開発・ご提供することで、当行はオンリーワンのリテールビジネスモデルを構築・推進していきます。
マーケットビジネス
~ポートフォリオの最適化で、飛躍的に収益向上を目指す~
市場運用に関しては、私たちの運用原資はお客さまの大切な貯金であり、収益性と安定性を両立させた運用を行うことが重要です。
ゼロ金利・マイナス金利時代に当行は、「運用のパラダイムシフト」として、日本国債中心の運用ポートフォリオから、外国証券やプライベートエクイティファンド、不動産ファンドなど、多様なリスク性資産へのシフトを進めてきました。この結果、日本銀行によるマイナス金利政策導入直後の2015年度末に1兆円弱あった円金利資産からの収益が、2022年度末には約5分の1の規模にまで縮小した一方、リスク性資産からの収益は約1兆円まで拡大しました。
足許では、先ほど申し上げたとおり、円金利上昇トレンドを捉えた「円金利ポートフォリオの再構築」を通じて、日本国債への新規投資を積極的に進めています。円金利資産にも投資できる環境となった今、残高が約108兆円まで拡大したリスク性資産については、残高を積み上げる数値目標ありきではなく、リスク・リターンやポートフォリオの安定性・耐久性などを重視しながら質を高めていきます。プライベートエクイティファンド、不動産ファンドを含む戦略投資領域への投資も、引き続き優良ファンドへの選別的な投資に注力します。また、米国の通商政策の影響で市場環境には不確実性がありますが、同時に新たな投資機会が生まれる可能性もありますので、中長期的なポートフォリオ運営のさらなる高度化に向け、情報を集めています。
当行はいよいよ日本国債とリスク性資産を「車の両輪」とする、運用ポートフォリオ全体の最適化を図ることが可能な戦略ステージに入ってきています。円金利資産の収益が1兆円規模まで回復し、リスク性資産からも引き続き1兆円規模の収益を生み出すことができれば、合計2兆円の収益となります。もちろん、それに満足せず、さらなる収益水準の向上を目指します。他に類を見ない、本邦最大級の特色ある機関投資家として、着実に前進していきたいと考えています。
Σビジネス
~良質な案件を積み上げ地方創生に寄与~
「Σビジネス」については、中核となる100%出資子会社の「ゆうちょキャピタルパートナーズ株式会社」を設立し、2024年度から「ゆうちょらしいジェネラルパートナー(GP)業務」を通じた「社会と地域の未来を創る法人ビジネス」として本格始動しました。中期経営計画最終年度にGP業務関連投資残高4,000億円程度という目標を掲げましたが、未公開株式への投資という性質上、数字ありきではなく、投資の質を重視し、「力を足し合わせる」という「Σ」の理念を斟酌しながら丁寧に投資を進めていく考えとしています。この結果、2024年度のGP業務関連投資残高の実績は1,191億円となりました。
Σビジネスを進めるにあたっては、地域金融機関等との協業が重要と考えており、すでに一部地方では、当行がエクイティを提供する案件に、地域の金融機関からローンやエクイティをご提供いただくなど、多様な形態での協業実績が積み上がってきています。当行の全国13エリア本部による各地域の実情を踏まえたソーシング活動を起点とした投資案件も発掘し始めるなど、手ごたえを感じつつあります。
JPインベストメントや共同事業者とのΣビジネスの投資ビークルを通じた投資実行先も、業種別にみると、製造業、ホテルや外食サービス、情報通信業、ヘルスケア、事業承継系や地域ベンチャー、再エネ関連など、幅広い分野で複数の案件が出てきています。また人財育成の一環として、希望する当行社員を積極的に外部のファンド企業などへ出向させており、研修プログラムも含めて取り組み体制を強化しています。当行は、息の長い投資として、地域の協業パートナーとともに丁寧に、雇用創出などを含む地域経済の活性化に貢献できる形で進めていく考えです。
将来グランドデザイン
~お客さまに最も身近な金融プラットフォーマー~
「リテール」、「マーケット」、「Σ」の3つのビジネスの深耕を図る中で、日本郵政の議決権比率低下による新規業務の上乗せ規制が認可制から届出制に緩和されることにより、当行のビジネス機会や成長の可能性のさらなる広がりが期待できます。
これからも、邦銀随一のお客さま基盤という強みを起点にしつつ、「運用力の高度化・活用」や「投資助言・資産運用のさらなる深化」を通じたアセットマネジメント業務の展開や、「協業による新たな価値提供」を目指し、これまでのオーガニックな成長だけではなく、社会やお客さまのニーズの変化に機動的に対処していくためにも、「自前主義」にかかわらずインオーガニックな成長機会も取り込んでいきます。
また、「ATMネットワークのさらなる活用」も目指しており、例えば、すでに地方銀行とは、そのお客さまに向けて当行のATMネットワークを無料でご利用いただきながら、当行が手数料収入を得ていくような提携が進んでいます。当行、提携先の地方銀行およびそのお客さまにとってもメリットが大きいwin-winのビジネスモデルであり、引き続き取り組んでいきたいと思います。
さらに、「新商品を通じた利便性の向上」や「ライフステージに寄り添ったソリューションの提供」という視点では、社会の高齢化を踏まえて、将来的な世代交代や相続を見据え、信託や相続関連のサービスを充実させ、お客さまをサポートすることも考えられると思います。より具体的な構想については、次期中期経営計画でお伝えしていきます。
中長期の企業価値創造の道筋と経営体制の強化
他行対比で低い水準にあるROEを向上させることも、経営上の重要課題と認識しています。次期中計の早い段階で、ROE5%を達成するという目標は、あくまで通過点で、これを早期に達成したうえで、さらに飛躍的に向上させたいと考えています。
先ほど、マーケットビジネスで2兆円超の収益を目指したいという話をしましたが、当行の強みであるお客さま基盤、貯金残高という安定的な資金基盤の上に、当行の収益の大半を稼ぐマーケットビジネスの収益が着実に伸びていけば、ROEの飛躍的な向上は、実現可能性があると考えています。
その着実な推進のためにも、ポートフォリオ運営に関するガバナンスがきわめて重要です。当行には、ALM委員会などの専門委員会、経営会議、取締役会に加え、金融システムに造詣が深い独立社外取締役の山本謙三氏を委員長とする任意の「リスク委員会」を取締役会のもとに設置し、専門家も外部委員として招き、執行サイドが策定する市場運用の方針等を客観的にチェックするしくみを構築しています。このような体制を通じ、執行サイドに限らず皆で当行のポートフォリオの健全性や収益性を守っていると実感しています。
郵便貯金事業150周年とその先のありたい姿
2025年は、郵便貯金事業の創業150周年となります。この長い歴史を紡いできた当行の一番の強みは、なんといっても日本全国のお客さまからの信頼です。
しかしながら、2024年度に、郵便局において、お客さまから事前に同意をいただかないまま、お客さまの貯金の非公開金融情報を不適切に利用していた事例が確認されました。日本郵便への銀行代理業務委託元である当行にも監督責任および個人顧客情報の安全管理措置義務違反があり、私自身も責任明確化の観点から、役員報酬の減額が決定される等、大変重く受け止めています。
改めてコンプライアンスの徹底が重要であることは言うまでもありませんが、お客さま本位の活動を十分浸透させないまま営業推進を優先したことが、今回の事案の発生原因となっています。
私たち日本郵政グループ約36万人の社員のその先には、1億2千万もの口座を通じて約190兆円の貯金を預けてくださっているお客さまがいらっしゃいます。お客さまが貯金を預けてくださっているからこそ、私たちはマーケットビジネスやΣビジネスを展開できるのであり、お客さまからの信頼が起点となります。これからもしっかりとその信頼に応えていくため、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の営業活動が大前提であることを肝に銘じ、立て直しに向けて改革を進めていきたいと思います。
つい先日、月半ばの15日に、地方のとある郵便局のATMの前に多くのお客さまが並んでいらっしゃる姿を目にしました。その中には年金の支給日に現金を引き出しに来られている方もおられましたが、そのようなお客さまのニーズを実際に目にすると、私たちの全国ネットワークが、皆さまの生活インフラとして真に必要とされていることを強く実感します。小さなお子さまのお年玉や入学のお祝い金を預けに親子で店頭に来られることも多いのではないかと思います。誰もが気軽に立ち寄れる身近な銀行であることは、私たちの大きな財産です。
全国を行脚しながら社員に入社理由を尋ねると、多くの社員が「地元密着でお客さまのお役に立ちたい」と答えます。私たちは、日本の近代郵便制度を創設した前島密翁が遺された「縁の下の力持ちたれ」との信条を、組織風土の骨幹として大切にしてきました。お客さまに最も身近な銀行として、縁の下からお客さまの人生をサポートしていく、そのような姿をこれからも目指していきたいと考えています。
企業価値向上と社会課題解決の両立を通じてサステナブルな経営の実現を目指すため、当行では、「日本全国あまねく誰にでも『安心・安全』な金融サービスを提供」、「地域経済発展への貢献」、「環境の負荷低減」、「多様な人財の活躍、ガバナンス高度化の推進」という取り組むべき重点課題(マテリアリティ)を設定していますが、郵便貯金事業創業以来の150年の歴史を振り返ってみると、私たちの存在はこれまでも、事業活動を通じて社会課題の解決に取り組み、さまざまなステークホルダーの皆さまへ価値を提供することで成り立ってきたと考えています。
投資家・株主の皆さまに対しては、ROEの持続的な向上を通じて企業価値を向上していきます。お客さまに対しては、全国津々浦々、誰一人取り残さず、リアルとデジタルの両面から商品・サービスの質や利便性を高め、より高度な金融サービスを提供していきます。そして、それを支える社員とは、力を合わせて変革を推進していきたいと思います。
今後も、さまざまなステークホルダーの皆さまに向けて提供価値の向上を図ってまいりますので、引き続きご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。