社外取締役
指名委員会委員長
海輪 誠
当社のWebサイトは、スタイルシートを使用しております。
お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
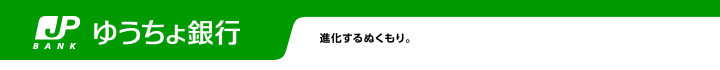
ホーム > IR情報 > 決算・IRライブラリ > 統合報告書・ディスクロージャー誌 > 社外取締役メッセージ

社外取締役
指名委員会委員長
海輪 誠
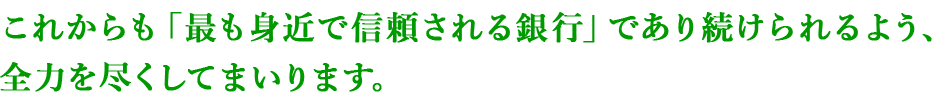
私は東北電力株式会社に長く勤務し、2010年からの10年間は取締役社長・会長を務めました。社長就任早々に東日本大震災が発生しましたが、「地域の復興は電力から」を合言葉に迅速な復旧に注力するとともに、電力小売自由化、送配電事業分社化など創業以来の事業変革も進めてまいりました。
東北電力は創業以来、「地域社会との共栄」を経営理念に掲げ、国民生活や産業に不可欠なインフラである電気事業を通して地域の発展を目指してきました。これは会社のDNAとなっており、私自身も自然災害や事故、燃料市場変動などさまざまな環境変化に遭遇する際、いつも念頭に置いたのは「どうしたら地域の皆様に貢献できるか」ということでした。
事業分野や設立経緯は異なりますが「社会と地域の発展に貢献」をパーパスとして掲げるゆうちょ銀行とはさまざまな類似性があると感じており、電気事業のトップを経験した者として、社長はじめ執行の皆さんにお伝えしていることが2点あります。
1点目は「危機管理は経営トップの最大の仕事」ということです。
私が東日本大震災後の経営危機を通して得た最大の学びは、企業にとって最も肝要なことは「危機管理」であり、「備え」がその成否を決めるということでした。ひとたび危機管理に失敗すれば企業の存続さえ危うくなる例は枚挙にいとまがありません。
平素から危機管理のシミュレーションや訓練を行い、組織整備や人財育成を通じて備えること、そしてトップ自らが最前線に立つ気概を持つことが重要です。ゆうちょ銀行にとっては、自然災害のみならず市場運用リスク、システムリスクなども大きな危機管理のテーマであり、リスク委員会を設置して外部の専門家も加えた監督体制を構築しています。これら危機管理については執行任せにすることなく、社外取締役としても最大限の注意を払っていかなければならないと考えています。
2点目は「地域社会と誠実に向き合う」ということです。
これも東日本大震災の話になりますが、震源に最も近かった女川原子力発電所は、当日中に安全停止させたうえで緊急避難的に周辺住民の受け入れを決断し、多くの方々が発電所体育館で避難生活を送りました。円滑な避難ができたのは、平時からの対話の積み重ねによる信頼関係があったからこそと考えています。迅速な復旧作業に加え、ここでも自分たちのことはさておき「地域の復興は電力から」という強い使命感を実感しました。
ゆうちょ銀行の強みは全国に広がる郵便局ネットワークと邦銀随一の顧客基盤であり、「最も身近で信頼される銀行」を目指す姿としています。裏を返せば、地域の皆様のご支援なしには事業が成り立たないということです。だからこそすべての業務で地域のお客さまに誠実に、親身に寄り添うことが重要であり、新たなΣビジネスも同様に地域経済の発展に貢献するものでなければなりません。
一方、ゆうちょ銀行も含め日本郵政グループにおける不祥事件は、私が社外取締役に就任した2019年以降においても発生しています。誠に残念ながら最近も、郵便局において貯金の非公開金融情報の取り扱いに関する法令違反の事案が発生しました。さらには、郵便局等において業務上横領などの不祥事件も複数発生し、グループの企業体質についてもご批判をいただいているところです。郵便局において発生した事案に関しても、ゆうちょ銀行には業務委託元としての監督責任があります。日本郵政グループに信頼をお寄せいただいたお客さま、株主など多くの皆様にご不安、ご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。
これら不祥事件の発生によって、日本郵政グループがお客さまや地域・社会からの信頼を失い、ひいては大切な顧客基盤を失いかねないことを懸念しています。今後、教育・研修やモニタリング強化など再発防止策を徹底することはもちろんのこと、受委託の関係にとどまらず日本郵便を共同パートナーと位置づけた業務体制に見直すなど抜本的な対策を検討していく必要があると考えています。
このような不祥事件発生の根本原因には企業文化やガバナンスの課題もあるとの認識から、ゆうちょ銀行の取締役会はガバナンス向上に取り組んでいます。
取締役会の多様性確保(独立社外取締役比率6割以上、女性比率3割以上等)、リスク委員会の設置、独立社外取締役会議の開催、幹部研修への参加、現場視察・社員との対話などにより、業務執行に対する社外取締役の理解がより深まりました。これらを受け、取締役会では多様なバックグラウンドにより、個別議案のほか中期経営計画などの事業戦略についても自由で活発な議論が交わされています。また、グループ会社間の情報共有・コミュニケーション強化のため、日本郵政におけるグループCxOの設置や各社社長の懇談会なども開催されるようになりました。このように、ゆうちょ銀行のガバナンスは着実に進化していると評価していますが、さらに実効性を上げられるよう不断の努力を続けたいと思います。
ゆうちょ銀行は、豊富な資金量をバックに国内外マーケットで順調な収益を確保し、ここ数年は経営計画を上回る利益水準を達成していますが、市場の期待水準とは未だ乖離があると認識しています。今後は、マーケットビジネスで適切なポートフォリオ運用によってさらなる収益拡大を目指すとともに、リテールビジネスではゆうちょ通帳アプリなどのデジタルチャネルとリアルチャネルの融合により顧客基盤の維持を図り、地域への新たな資金循環システムとしてスタートしたΣビジネスを軌道に乗せていく計画です。
この度、日本郵政によるゆうちょ銀行株式の売出しが行われ、日本郵政のゆうちょ銀行株式保有割合は50%以下となりました。今後は、郵政民営化法による「上乗せ規制」が部分的に緩和され、新規ビジネスへの挑戦も容易になります。なお、日本郵政による株式の処分がいっそう進んだ場合でも、日本郵政グループの一員としてのゆうちょ銀行の役割は不変であると考えますが、これまで以上に自律的かつ少数株主に配慮した経営が望まれます。収益性と社会貢献との調和、グループ経営のあり方など、社外取締役からも提言してまいりたいと思います。
私は、指名委員会の委員長も務めており、取締役候補者に係る指名基準の策定および取締役候補者の株主総会提出議案の決定、代表執行役社長の後継者計画の策定などを通じて、ゆうちょ銀行のガバナンス向上に積極的に関与してきました。
昨年、これまで主に市場部門をけん引してきた笠間貴之氏が社長に就任しました。足元の不祥事件への対応、完全民営化に向けた進展と新たなビジネスモデルへの挑戦など課題山積の中でのスタートですが、このような時こそ「危機管理は経営トップの最大の仕事」と覚悟を決め、若さと行動力でリーダーシップを発揮し、将来にわたる成長と持続可能性の礎を築いていただくことを期待しています。微力ながら私も全力でサポートしてまいります。

トップメッセージ、報酬・監査・リスク委員長メッセージ、財務・資本戦略 担当役員メッセージについては、こちらをご覧ください。