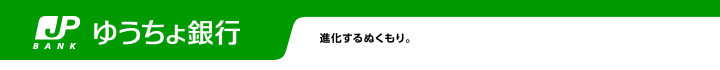
ホーム > IR情報 > 決算・IRライブラリ > 統合報告書・ディスクロージャー誌 > 報酬・監査・リスク委員長メッセージ
報酬・監査・リスク委員長メッセージ
報酬委員会

社外取締役 天野 玲子
報酬委員会の役割は、ゆうちょ銀行のパーパス、経営理念、ミッション、中期経営計画などの実現に資する取締役・執行役の報酬等の内容に関する決定の方針および個人別の報酬等の内容の決定です。
報酬等の内容の決定については、透明性・客観性・公平性の確保に留意しつつ、定量評価および定性評価により構成された業績連動指標に基づいて実施しています。具体的には、定量評価では財務指標などで定められたKPIの達成度によって評価を行い、定性評価では企業価値向上に資する非財務指標などの達成度によって評価を行っています。
ゆうちょ銀行は、執行役に業績連動型の報酬制度を導入していますが、報酬委員会において積極的に議論を重ねた結果、2024年度からは、新たに短期業績に連動した金銭報酬制度(年次賞与)を導入しました。また、代表執行役社長を含む全執行役の報酬にESGに関する指標を適用していますが、年次賞与のうち15%については、ESG関連のKPI達成状況によって評価することとしました。
報酬は企業が持続的に成長するために取締役・執行役にとって重要な項目です。さらに、経験豊富で優秀な人財を確保するためにも、納得感のある報酬体系の構築は最も重要なテーマの一つです。ゆうちょ銀行がこれからも成長し続けるための役員報酬制度はどうあるべきか、今後どのような方向性で報酬を検討していくべきか、環境の変化を踏まえて現在の報酬水準は妥当なのか、企業価値向上や成長に結び付く適切な報酬となっているのかなど、委員長として問題意識を常に持ち続けて、委員との議論をより深め、ゆうちょ銀行の発展に貢献していきたいと考えています。
監査委員会

社外取締役 河村 博
ゆうちょ銀行のパーパスを実現するためには、コンプライアンスの徹底のみならず、株主の皆様の利益を守りつつ、持続的な成長のための事業戦略が適正に実行されているかを監督することが非常に重要だと考えています。取締役会が果たす監督機能の一翼を担う監査委員会として、ルールへの準拠性や重要な経営方針等との適合性の監査にとどまらず、各委員の知見、経験等を踏まえ、今後の課題やあるべき姿などについての指摘、助言も行っています。また、各委員が各地のエリア本部、直営店、郵便局などフロントラインを訪れ、実情や課題の把握に努めています。
2024年度においては、ゆうちょ銀行のパーパスと経営理念のもと、ミッションや中期経営計画などの実現に資するため、部内犯罪対策そのほかコンプライアンス態勢の強化、サイバー攻撃防御を含むリスク管理、危機管理態勢の強化等「内部統制システムの改善に向けた取り組み」、人的資本経営の推進、さらに、デジタルサービス戦略などを含むリテールビジネスやΣビジネス等「事業の維持・発展に向けた取り組み」、「より実効性のある内部監査の実現に向けた取り組み」などを重点的に監査しました。リスク管理態勢等の強化についてはリスク委員会と連携し、重複を避けつつ効率的な監査活動を行うようにしており、フロントラインへの往訪の結果を踏まえ、働きがいのある職場の実現に向けた議論なども行っております。
そのような中、誠に遺憾ながら、ゆうちょ銀行の非公開金融情報について委託先である日本郵便での不適切な利用事案が発生しました。お客さまにご不安、ご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。このような事案が発生したことを厳粛に受け止め、今後、同様の事案が二度と起きぬよう、グループ各社と連携して、原因の分析や防止策の実効性などについての検証を行うとともに、監査を行ってまいる所存です。
パーパスの実現に向け、今後も監査委員会の監査活動をさらに充実させることにより、ゆうちょ銀行のガバナンス体制をしっかりとサポートできるよう、監査委員会の重要な役割をしっかり果たしてまいります。
リスク委員会

社外取締役 山本 謙三
リスク委員会は、指名、報酬、監査の法定3委員会と並んで、取締役会のもとに設けられた任意の委員会で、ゆうちょ銀行が抱えるリスクに関し、重要事項を審議し、取締役会に報告、助言を行うことを役割としています。「リスク」といえば、ゆうちょ銀行のすべての業務がかかわりますが、同委員会では、当行にとって潜在的なリスクの大きい市場・ALM(資産負債管理)関連やシステム関連を中心テーマに据え、外部の専門家を交え活発な議論を続けています。
2024年度は、①24年3月の日本銀行による異次元緩和の解除以降、国内金融市場が「金利ある世界」に回帰してきたこと、また、②25年1月の米国のトランプ第47代大統領就任をきっかけに世界経済や金融市場が不透明感を増したことなどを踏まえ、多様な角度から金融経済情勢を点検してきました。
また、リスク管理にあたっては、特にストレス・テストを重視し、将来リスクが顕在化する場合の想定シナリオを複数策定したうえで、それぞれの影響度と対応計画の妥当性を検証しています。
実際、2025年度入り後には、トランプ関税の発動をきっかけに、世界の経済金融情勢が一気に不確実性を増しました。「高率の相互関税適用」といった具体的な事態を前もって想定するのは難しいわけですが、例えば世界経済がスタグフレーション(物価高と景気悪化の並立)に陥るようなシビアな想定シナリオを策定し、あらかじめリスクを限定するための手順を共有しておくことは、いざというときの機動的な対応に資するものと考えます。
また、システム関連では、当行は、大きな社会課題となっているサイバー攻撃からの防御や不正送金被害の防止のためのしくみを強化してきており、リスク委員会も、その着実な進捗を確認しています。
このほか、Σビジネスのリスク管理体制などに関する議論も深めてきました。いずれのテーマもリスク委員会と執行部との活発な議論を通じて、取締役会の監督機能強化に寄与したものと考えています。
お客さまからお預かりした大切な貯金を守り続けていくため、今後とも当行が抱えるリスクを注視し、過大なリスクテイクを回避しつつ収益力の着実な向上が図られるよう、リスク委員会の職責を果たしていく考えです。


