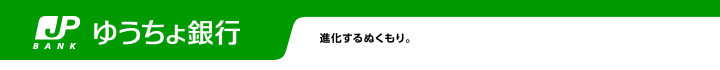
ゆうちょの新社会人応援!
新社会人として日々頑張るあなたに、知っておくべきマナーやお金に関する疑問をQ&A形式で分かりやすく解説します。これからの社会人生活をより充実させるための知識を身に付けましょう!
ゆうちょがスマート!
ご自宅やお出かけ先からも、
ゆうちょ口座へ便利にアクセス!
まだゆうちょ口座をお持ちでない方は…
※無通帳型総合口座「ゆうちょダイレクト+(プラス)」のお申し込みです。通帳発行(有通帳口座への切り替え)をご希望の場合は、通帳繰越機能付きATMや窓口で、口座開設後2か月および初回に限り無料でお手続きいただけます。
キホン
監修:齋藤 孝さん
(明治大学文学部教授)

-
まずはチェック! 報·連·相の基本

仕事の経過や状況を知らせることで、上司に自分の状況を正確に把握してもらう。

あなたが得た情報を、そのまま上司や関係者に伝える。その際、臆測や意見は不要。

自分だけでは判断できない事案について、上司からアドバイスや指示をもらう。
「伝えること」の基本構成
1 趣旨
2 結論・結果
3 判断のポイント
4 最後に、今後のアクションの確認
1〜4を簡潔に伝えられるよう、意識してみましょう。役立つフレーズ
業務の変更などを報告するとき
△「知っておいてください」
○「お含みおきください」
スケジュールの変更や業務進行に条件が付いてしまうことを、上司やお客さまに伝える場合、心にとどめてほしいとお願いする「お含みおきください」というフレーズを使うと、丁寧に理解を求める表現になります。
業務の進捗を伝えるとき
△「とりあえずの日程です」
○「暫定的な日程です」
「とりあえず」は、どこか適当で、間に合わせな印象を与えます。どちらも同じ「仮に決めておく」という意味ですが、「暫定的」と言うと、応急的な処置であるという意図がしっかりと伝わり、ビジネスの場にふさわしい表現になります。
-
まずはチェック! 電話対応の基本
電話を受ける
コール3回以内に取りましょう
取るまでに時間がかかってしまった場合は、冒頭に「大変お待たせいたしました」と一言添えましょう。
受ける前に必ずメモの準備を
相手の社名、名前、用件などを箇条書きでメモし、聞き漏らしや伝え忘れをなくしましょう。
「もしもし」は、NG!
電話を受けるときの第一声は、「はい」がオーソドックス。明るくはきはきした声で「はい、○○です」と、社名や部署名、自分の名前など、ケースにあわせて最適な情報を伝えましょう。「お電話ありがとうございます」と付け加えるとより丁寧です。
電話を取り次ぐ
◆基本の流れ
「お繋ぎいたします。
少々お待ちくださいませ」
と言い保留ボタンを押す。
↓
「○○(あなたの名前)ですが、□□社の△△様からお電話が入っています」
簡単な用件を聞いていたら
「・・・の件でお電話が入っています」と伝えましょう。◆受話器の取り扱いでも好印象を
ガチャッといった雑音を立てないよう受話器は丁寧に取り扱いましょう。
通話後は、まず指でフックを押さえて電話を切り、その後に受話器を置きましょう。
役立つフレーズ
承諾の意思を伝えるとき
△「了解しました」
○「承知しました」「かしこまりました」
OKの意味を表す「了解しました」はよく使われる表現ですが、ビジネスで、目上の人、お客さまや外部の人に対する場合は、「承知しました」「かしこまりました」という言葉がふさわしいといわれています。
電話の内容を確認するとき
△「繰り返します」
○「復唱いたします」
電話の内容を確認する場合は、「復唱いたします」と言い、繰り返すのがスマートです。特にメールアドレスは、電話でのやりとりでは間違えやすいもの。ミスを避けるためにも、復唱する習慣を付けましょう。
-
まずはチェック! ビジネスメールの基本

1.メールアドレスを登録する際、「様」を付ける習慣付けを。名前だけ登録すると、メールの表示上で呼び捨てにしてしまうことに。
2.件名で内容が分かるように。
3.文頭に、「株式会社△△△△ □□部 ○○様」とあて名を入れ、「いつもお世話になっております」といった簡単なあいさつを。その後、初めての相手には、「□□□□株式会社の○○でございます」といった自己紹介も。
4.用件は簡潔に、分かりやすく。1行が長くなりすぎないように改行し、本文の長さは20行程度が目安。
5.最後に、「署名」を入れる。
役立つフレーズ
相手の意見や知識を知りたいとき
△「教えてください」
○「ご教示ください」
「教えてください」よりも、「ご教示ください」の方が知的な印象があります。口頭で使うには少しかしこまって堅苦しい感じがしますが、ビジネスメールなどの書き言葉として使うとちょうどよい表現です。
本当は直接会って伝えたい旨を伝えるとき
△「メールで失礼いたしますが」
○「略儀ながらメールで」
相手と直接会って伝えたいあいさつやメッセージを、メールで済ませなければいけないときは、正式な手続きを省いて簡略化した方法を示す「略儀」という言葉を活用すると、誠意とともに、知識の深さを相手に伝えることができます。

学生と社会人では、人との付き合い方はもちろん、お金との付き合い方も違ってきます。今のうちに解決しておきたいお金に関する疑問について、データとともにお答えしていきます。
-

基本給等の金額から税金や保険料が天引きされるからです。
手取り額は基本給や手当から税金や保険料が差し引かれた金額です。税金は「源泉徴収」というしくみによって毎月天引きされ、初年度は所得税のみですが2年目の6月からは住民税も徴収されます。また、保険料として、雇用保険料・厚生年金保険料・健康保険料などが引かれます。給与の支給とともに渡される、給与明細書を確認しておきましょう。
給与明細書の見方
差引支給額(手取り額)(1)は、勤務状況をベースに計算された総支給額(2)から、所得税などが控除(3)されたうえで決まります。

-

社会人1年目は、1年間で平均52万円です。
1年間で平均52万円ということは、月々4.3万円ほど。ボーナスの一部を貯蓄に回すとしても、新社会人にとって、決して簡単に達成できる金額ではありません。しかも、新社会人の夏のボーナスは、本来の金額の一部が一時金として支払われることが多いようです。まず、可処分所得(収入から必要な支出を除いたもの)から貯蓄分を振り分けたうえで、お金を使う習慣を身に付けましょう。
社会人1年目の1年間の貯蓄額

出典:ソニー生命調べ「社会人1年目と2年目の意識調査2025」
-

スマートフォン用の家計簿アプリを利用する人が増えています。
頑張って働いた給与を有意義に使うためにも欠かせないのがお金の収支管理ですが、デジタル世代のみなさんにとって紙の家計簿は面倒に感じることでしょう。そこでおすすめは、スマホ用の家計簿アプリ。スマホ決済やクレジットカードなどと併用すれば、支出の明細なども手軽に確認できます。
家計管理を行っている場合、
どのような方法で管理していますか?
出典:2024年 ゆうちょ銀行調べ
-

重視するポイントの上位は、手数料が安くどこにでもあること。
給与受取用の口座開設など、メインバンクを選択するポイントとして、「手数料が安い」や「便利である」とともに、多くの人が挙げているのが、「どこにでもある」こと。具体的には、ATMや店舗の多さといえるでしょう。飲み会などで急に現金が必要になった場合も、ATMや店舗が家や職場の近くにあれば、時間や引き出し手数料を節約できます。
メインバンクを利用するときに
重視する点は?
出典:2024年 ゆうちょ銀行調べ
-

インターネットバンキングなら、
いつでもどこでも振り込みや現在高の確認などが可能。パソコンやスマホから、いつでもどこでも振り込みや残高照会などができるのがインターネットバンキングです。例えば、お昼休みにオフィスで家賃の支払いを済ませたり、現在高の確認をしたりできる便利さから、利用が急速に拡大しています。近年では、さまざまな機能を提供する銀行のスマホ向けアプリもあります。
インターネットバンキングの利用経験率

インターネットバンキングで
利用している/していたサービス
出典:2025年1月マイボイスコム調べ「インターネットバンキングの利用に関するアンケート調査」
その他のお役立ち情報を記載した
PDF版はこちら


